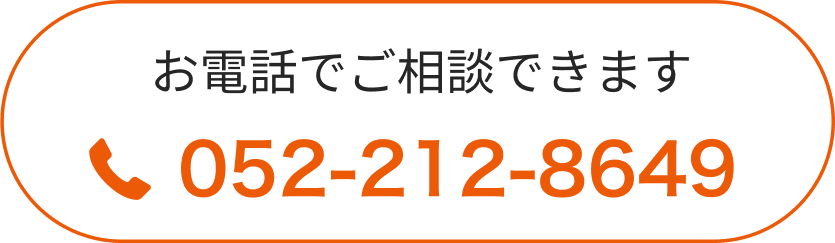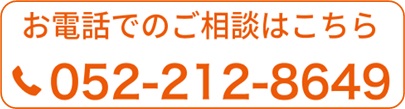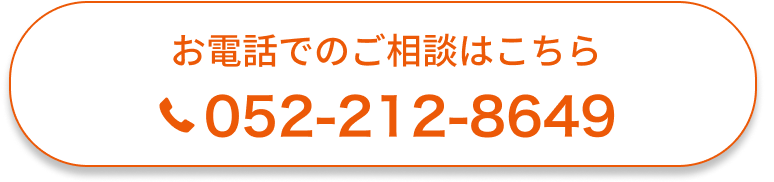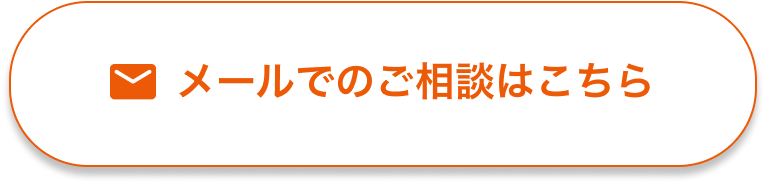在庫/WMS(倉庫管理システム)“ここだけスクラッチ”:既存システムと噛み合わせる方法
1.はじめに

「今の販売管理は動いている。だけど在庫の現実と、画面の数字が合わない」。
名古屋・愛知の現場でよく聞く声です。
システムを丸ごと入れ替えるのはリスクが大きい。
一方で、棚卸・入出庫・ロケーション移動の“詰まり”を放置すれば、欠品と余剰が同時に起こる。
この記事は、既存の販売管理・会計は活かしながら、
在庫/WMS(倉庫管理システム)の“ここだけ”をスクラッチで噛み合わせる現実解を、読み物としてまとめたものです。
2. まず“噛み合わせ”の設計から始める
やるべき順番は、WMSを買うか作るかの比較ではありません。
“どこで現実と数字が離れるか”を地図化することです。
入庫で離れるのか、移動で離れるのか、棚卸で離れるのか。
離れている場所に、軽いスクラッチの歯車を入れて、既存システムと噛み合わせる。これが最短ルートです。
歯車の条件は三つ。
1)現場で1秒速い、
2)例外に強い、
3)既存の台帳に正しく息を合わせる。
この三つが揃うと、全入替より早く、低コストで効きます。
3. “ここだけスクラッチ”のコア領域
1)スキャン一発で“現実”が台帳に追いつく場所
入庫・ピッキング・移動・棚卸。現場はテンキーとバーコードの世界です。
ここにモバイル画面(PWA)を差し込み、スキャン→数量→確定を指が止まらないテンポで回す。
ロケーション、ロット/シリアル、期限、割付先の情報は、スキャン時に自動で候補が出る。
人が迷う時間をゼロにすれば、数字は勝手に合っていきます。
2)“例外先行”で設計する
不足・余剰・破損・見当たらない・移動中。
この例外こそ毎日起きる現実です。
最初から例外ボタンを置き、理由コードを選べばそのまま差異台帳に落ちる。
棚卸は“差異の理由を集める作業”に変わり、後処理に強くなります。
3)既存システムとの呼吸(API/CSVの現実解)
販売管理の受注・発注・在庫台帳はそのまま使う。
スクラッチWMS側は、明細ID・品目コード・ロット/シリアル・ロケーション・数量・時刻を持ち、受発注明細と突き合わせます。
連携はAPIがあればAPI、なければCSVバッチで十分。
重要なのは、連携タイミングの約束
(例:1時間ごと、締め時点、イベント発火)を決めること。
息が合えば、台帳の“ズレ時間”は縮みます。
4. 名古屋の現場で効いた“画面の顔(インターフェイス)”

1)入庫(仕入/戻入)
納品書のバーコードを読むと、入庫候補が並びます。
品目をスキャン→数量→ロケーションを提案→確定。
ロット/期限は画像つき入力でミスを防ぐ。
十数秒で一行が終わるテンポが、最速の正しさです。
2)ピッキング(引当/出庫)
伝票番号を読み込むと、最短動線のピック順で候補が並びます。
ロケーション→品目→数量の順にガイドされ、代替ロットが必要なら即提案。
“見当たらない”ボタンで差異台帳に落ち、在庫の嘘はその場で消します。
3)棚卸(循環/全数)
ロケーション単位で毎日少しずつ回す運用に変えます。
スキャン→数量→差異理由。差異は自動で調整仕訳候補になり、承認した分だけ販売管理に流れる。月末の“全数マラソン”は、もうやめられます。
5. データの“正本”と番号の約束

在庫の正本はどこか。
答えは「販売管理の在庫残高(台帳)」と「WMSのトランザクション(現実の履歴)」を
役割分担することです。
台帳は金額が正しい、WMSは動きが正しい。二つを結ぶのは番号です。
受注番号・発注番号・入出庫番号・ロケーション・ロット/シリアル。
番号が噛み合えば、どれだけ動いても後追いができます。
だから、スクラッチ側は番号を裏で自動発番し、既存の番号は参照して紐づける。
人が番号を決める場面は、極力なくします。
6.つまずきやすいポイント(でも避けられる)
現場の“呼び方”が揃っていないと、ロケーションやロットの命名がブレます。
最初に呼び方辞書を1ページで決め、画面の選択肢に埋め込むだけで迷子は激減します。
もう一つは、帳票の完コピ沼。出庫伝票や棚卸表を昔の様式で完全再現しようとすると、途端に重くなる。
最初はA4一枚のミニ版で十分。法定・対外帳票だけ厳密に、社内帳票は“数字が合うこと”を優先します。
最後に、連携のタイミング。リアルタイムが正義に見えますが、実務は“決まったタイミングで確実に”のほうが強い。
最初は時刻スケジュールで安定化し、必要な箇所だけイベント連携へ移行するのが安全です。
7.名古屋・愛知のスナップ実例
豊田の部品メーカーA社は、ピッキングでの“見当たらない”が日常茶飯事。
WMSに例外ボタンと差異台帳を作ると、翌月から差異が半減。循環棚卸に切り替え、棚卸時間は約1/2になりました。
一宮の繊維B社は、ロットとロケーションが現場ごとに呼び方バラバラ。
呼び方辞書を作って画面の選択肢に埋め込むと、在庫の捜索時間が3割減。
名古屋市の商社C社は、販売管理の入替を避けつつWMSだけ強化。
CSVバッチ連携で1時間ごとに台帳へ反映し、欠品・余剰の同時発生が激減。
全入替より1/3の費用・期間で効果が出ました。
8.よくある質問に先回りしておきます
Q. APIがない既存システムでも連携できる?
A. できます。CSVの送受信+固定スケジュールで十分に実用。将来APIが整ったら置き換えられる設計にしておきます。
Q. バーコードの規格をどうする?
A. まずは社内規格(Code128など)で統一。取引先ラベルは“読み替え辞書”で吸収し、混在期を乗り切ります。
Q. リアルタイム更新は必須?
A. 必須ではありません。締め・1時間ごと・イベント発火の三段階から開始。安定したら必要箇所だけリアルタイムに。
9.次の一歩
まずは無料相談でお気軽にご相談ください
#スクラッチ開発 #オーダーメイドシステム #DX

この記事を書いた人
株式会社ウェブロッサムの
代表:水谷友彦
中小企業の業務効率化を
デジタル戦略でサポート