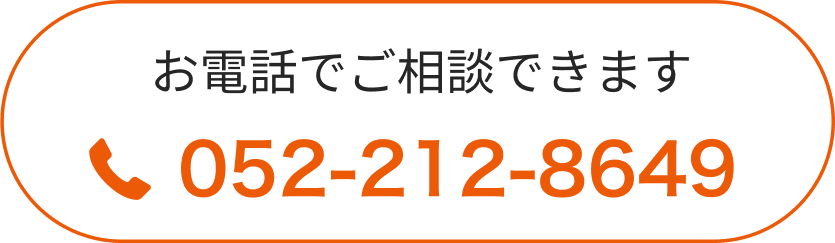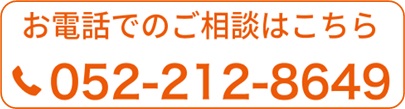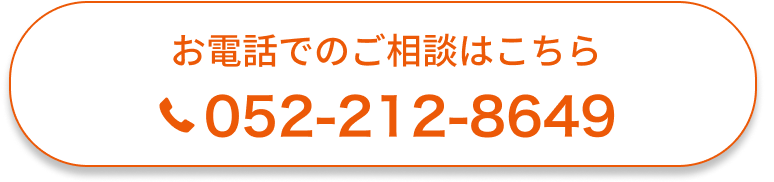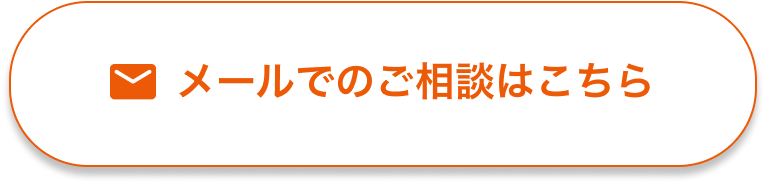リアルタイム進捗×IoT:止めない工場を小さく作る
1.はじめに
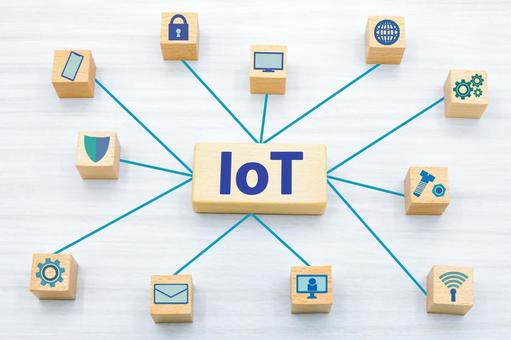
「止めない」「待たせない」。名古屋の工場で本当に効くIoTは、派手な見た目ではなく、
いま起きている小さな詰まりを10分以内に片づける仕組みです。
高価な装置を一気に入れるより、1ラインの“見える化”を小さく始めるほうが、
速く・安く・確実に効きます。
本稿は、リアルタイム進捗×IoTを“読み物”としてやさしく解きほぐし、最短で効果を出す道筋をまとめました。
2. まずは「どこが止まるのか」を10分で言語化
最初の仕事は技術選定ではありません。
どこで止まるかを短い言葉にすることです。
ワークが溜まるのは前段か後段か、検査に偏りがあるのか、段取り替えの時間が読めないのか。
現場の“言い回し”でいいので、止まり方の型を三つほど挙げます。
ここが決まると、何を拾って何を捨てるかが見え、センサーや画面の設計が自然と絞られます。
3. 小さく作る:1ライン×3信号×1画面
最小構成はシンプルです。
稼働(RUN)・停止(STOP)・段取り(SETUP)の三信号を拾い、1画面に時系列で出す。
PLCや設備の信号が取れればベストですが、
取れなくても人のワンタップと光電センサーの組み合わせで始められます。
重要なのは、誰が見ても同じ意味になること。
色、音、文言を現場の言葉に合わせます
(例:「段取り中=工具替え」「停止=材料待ち」)。
4. 現場UIの“顔”:紙を責めずに置き換える

紙の良さは“速さ”です。
だからUIは紙より速いことが条件になります。
作業者はテンキーと大きなボタンだけで、理由を1秒で選べる。
監督はライン一覧のタブをスワイプで巡回でき、
赤(停止)→タップ→原因→対応者割り当てまでが3タップ。
ダッシュボードは“壁に貼る管理ボード”ではなく、今日の行き先を教える顔にします。
グラフより、いま対応すべき順番が先に目に入ることが大事です。
5. センサーとつなぎの現実解(難しい話は最小限)

機械から信号が取れるなら、PLCの離接点/カウントをゲートウェイ(小型PC/エッジ端末)に入れ、MQTTやHTTPでサーバーへ送ります。
取れない場合は、光電/近接センサー+小型コントローラ(例:ESP系)で“通過”を拾い、
1ショット=1個としてカウント。
どちらでも、ネットワークは工場LAN内→クラウドの順に段階化し、
切れてもバッファしてあとで同期できる構成にします。
写真や不良票の添付は同じ画面で。
設備アラートに一言メモ+写真が紐づけば、解析が“記憶頼み”から解放されます。
6.数字の持ち方:OEE(設備総合効率)より“現場の3指標”
OEEをいきなりやると挫折しがちです。
最初は「停止回数」「停止時間」「良品数」の三つだけを時系列で押さえます。
停止の理由は最初から細かくせず、5〜7種類にしぼる。
月次の集計より、日次の振り返り(10分)を優先。
昨日の赤の山にだけ向き合い、原因と対策の一行メモを残します。
この地味な繰り返しが、段取り時間の短縮や材料欠品の予防に直結します。
7.名古屋・愛知のスナップ実例
豊田の加工A社では、
停止理由が「その他」に偏り、対策が進みませんでした。
ボタンの文言を現場の言葉に合わせて5種類に減らすと、停止の山が明確化。
段取りと材料待ちに分けて対策し、停止時間が2割減。
一宮の組立B社は、
検査前の滞留が慢性化。
光電センサーで通過個数を取り、検査台の人タップと突き合わせると、特定時間帯の段取り遅れが見え、シフトと治具の持ち方を調整。
日次の遅延がほぼ解消しました。
名古屋市内の装置C社は、
IoTの一斉導入で頓挫経験あり。
今回は1ライン・1画面から再開し、写真+一言メモを停止に紐づけ。
初月で“効く停止”が判別でき、投資先の優先順位が定まりました。
8.よくある質問に先回りしておきます
Q. 既存MES(生産実行システム)や設備監視が一部入っています。重なりませんか?
A. 重ねる必要はありません。“詰まりを10分で解消する画面”に役割を限定すれば、共存できます。データはAPI/CSVで取り込めます。
Q. センサーが取れない設備があります。
A. 取れる所は信号から、取れない所は人タップ+簡易センサーで始めます。後から置き換え可能な設計にします。
Q. OEEまでやるべき?
A. いきなりは不要。停止回数・停止時間・良品数の三つが日次で回るようになってから、段階的に広げれば十分です。
9.次の一歩
まずは無料相談でお気軽にご相談ください
#スクラッチ開発 #オーダーメイドシステム #DX

この記事を書いた人
株式会社ウェブロッサムの
代表:水谷友彦
中小企業の業務効率化を
デジタル戦略でサポート