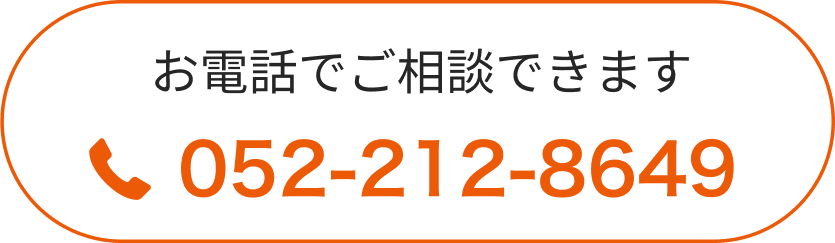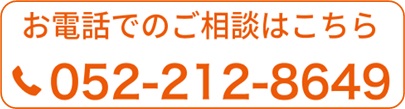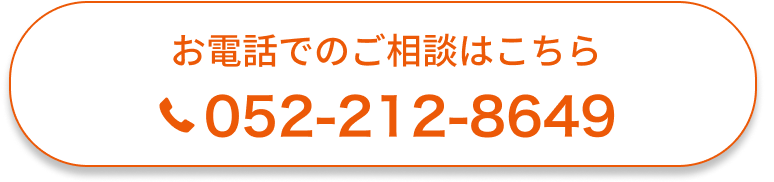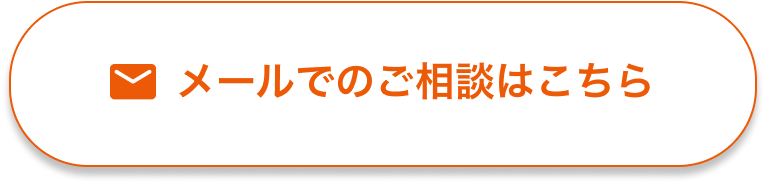製造業の原価管理“必須8画面”:受発注〜請求を一気通貫
1.はじめに

「数字は合っているのに、現場の感覚と合わない」。
名古屋・愛知の製造現場で原価の相談を受けるとき、最初に浮かぶのはこのズレです。
受注、手配、工程、実績、請求——それぞれは正しいのに、一本の線でつながっていない。
Excelの間を人が埋め、確認の電話が増え、未請求や仕掛の管理が後手に回る。
この記事は、そのズレを断つための“必須8画面”を、読み物として一気に説明します。
三河・尾張・豊田・刈谷・一宮の実情に寄せ、スクラッチ開発(名古屋)でどう組み上げるかの勘どころまで踏み込みます。
2. なぜ“原価が合わない”のか(まずは順番の話)
原因は技術の難しさよりも、情報が流れる順番にあります。
見積原価は受注の段で決まり、実際原価は手配と工程で積み上がり、工数と出来高が日々の手触りを作り、最後に検収と請求で締まる。
どこか一箇所でも“横道のExcel”に落ちると、原価は遅れてやって来ます。
解決はシンプルです。受発注→手配→工程→実績→原価→請求という一本の線を、
画面の並びとしてそのまま体験に落とし込むこと。ここから“必須8画面”の物語に入ります。
3. “必須8画面”を物語として

1)受注/案件(原価の器を先につくる)
原価管理は受注の瞬間から始まります。
案件番号、仕様、ロット条件、見積原価と目標粗利を一枚で押さえ、
後続の画面すべてに流せる器にする。
ここで「何を原価として拾うか」を決めておくと、後ろの迷いが消えます。
2)手配・購買(材料と外注の“金額の芯”)
発注、仕入、単価履歴、納期、検収の流れを一つの画面で見渡せると、原価は急に素直になります。
外注の出来高に応じた検収や、単価の改定履歴、納期遅延のアラートまでを同じリズムで扱えることが肝。メールやFAXの世界を数字の世界へ穏やかに引き上げます。
3)工程計画(負荷と段取りの見える化)
BOMとルーティング、段取り時間、代替工程。
ガントで引っ張るだけの計画ではなく、
「今日どこが詰まるか」が一目で分かる負荷ビューが要ります。
優先順の入れ替えが原価にどう効くか、受注画面まで因果が戻るのが理想です。
4)作業実績(工数と出来高の呼吸)
現場はテンキー、スキャナ、タッチの1秒×100回/日の世界です。
開始/終了、出来高、ロス理由を止まらずに入力できること。
バーコードや作業コードで迷いを消し、残工数が自動で予測されると、
“あといくつ着工するか”が急に語りやすくなります。
5)在庫・ロット(入出庫と棚卸)
ロケーション、ロット/シリアル、有効在庫、先入先出。
ここを例外先行で設計します。
不足・余剰・移動中・返品といった“現実の揺れ”を先に定義し、
バーコードとあわせて棚卸の負担を半分に。原価差異の元凶は在庫に宿ります。
6)原価集計(材料/外注/労務/経費の着地)
見積原価と実際原価、差異の理由が品目・工程・案件の粒度で並ぶこと。
材料と外注は手配から、労務は実績から、経費は配賦ルールから集まる
——その道筋が見える画面に。月次締めの“暗算”がいらなくなります。
7)売上・請求(検収と未請求の可視化)
出来高請求、検収差異、締め、請求書PDF、会計仕訳の連携。
ここで重要なのは、未請求の残りを強調(赤など)すること。
原価は締まったのに、売上が立っていないという“空振り”を、その日その場で捕まえます。
8)ダッシュボード(“今日やるべきこと”の画面)
粗利率、原価差異、在庫回転、滞留ロット、負荷の偏り。
KPIの張り出しボードではなく、今日のアクションが分かる画面にします。
「この案件の外注単価が上がった」
「この工程の残工数が跳ねた」
——通知ではなく判断のきっかけを出すのが仕事です。
4. UIと運用:定着させるのは“正義”ではなく“摩擦ゼロ”
原価の正しさは、UIのやさしさに比例します。
テンキー最適化、貼り付けに強いテーブル、バーコードでの迷い消し、写真・証憑を同じ画面で完結
——この小さな体験の積み重ねが、教育より効きます。
画面の並びは、現場の動線に合わせて受注→手配→工程→実績→原価→請求。
そして、例外(不良、横持ち、代替、仮受け)を先に設計する。これだけで、現場は自然に“正しい数字”を生み出します。
5. 「ここだけスクラッチ」の切り方(ハイブリッド前提)

在庫や会計は既存システムを活かし、詰まっている所だけスクラッチでつなぐのが、
名古屋・愛知に多い製造業の実務で一番無理がありません。
データの正本(マスター/トランザクション)はスクラッチ側に置き、WMS(Warehouse Management System)や会計とはAPIやCSVで呼吸させる。
受注・原価・請求の根幹だけを自社のリズムで持つと、改修の自由度が段違いになります。
6.よくある落とし穴(回避の型つき)

帳票の完コピ沼は危険です。
最初は“実務に効くミニ版(法的・取引上の必須項目だけを満たし、1ページで印刷でき、現場の入力を増やさない最小構成の帳票)”で十分。法定・対外帳票だけ厳密に。
次に、品番/ロットの揺れを最後まで放置しないこと。
最初のスプリントからテストデータを入れ、統一ルールを決めます。
さらに、小さなPoCを惜しまないこと。PDF、バーコード、会計連携は早めに“できる/時間がかかる”を見切る。
最後に、ドキュメントとリポジトリの共同管理。ベンダーロックは技術でなく情報の閉じ方から生まれます。
7.よくある質問に先回りしておきます
Q. 既存の在庫/会計システムはそのまま使える?
A. 使えます。受注〜原価〜請求の根幹だけスクラッチにし、周辺はAPI/CSVで連携するのが王道です。
Q. 何から始めればいい?
A. まずは現場の1日の流れを書き出してください。要件定義チェックリスト(PDF)が役立ちます。書けたらMVP(最小限のプロダクト)の範囲をA/B/Cで決め、受注→請求の線を先につなぎます。
Q. どれくらいで効果が出る?
A. 最小構成なら2〜4ヶ月で“入力が軽くなった/未請求が減った”を実感できます。数字は差異/残工数/未請求の3指標で追うのが近道です。
8.次の一歩
まずは無料相談でお気軽にご相談ください
#スクラッチ開発 #オーダーメイドシステム #DX

この記事を書いた人
株式会社ウェブロッサムの
代表:水谷友彦
中小企業の業務効率化を
デジタル戦略でサポート