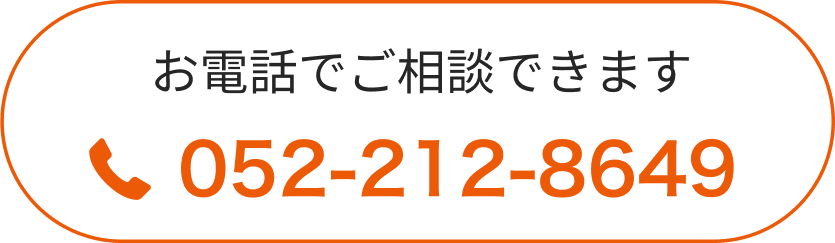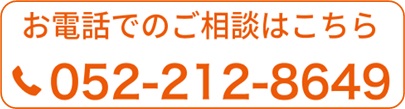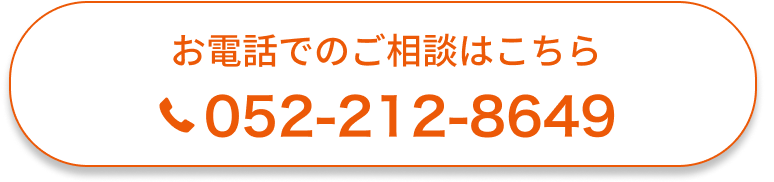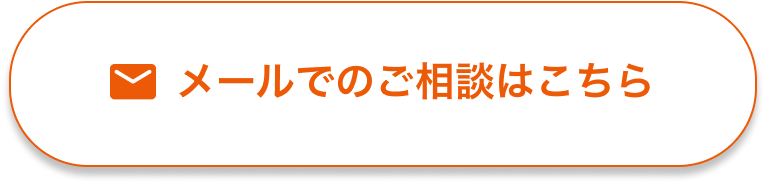スクラッチ開発の費用相場(名古屋版):内訳・期間・失敗コスト
1.はじめに

「スクラッチ開発の価格や相場(名古屋/愛知)って、結局いくらから?」。この質問に“実務の温度感”で答えるのが本記事です。
まず覚えておきたいのは、最初から完璧な一発見積を狙うより、今回はどこまで作るか(MVP)を先に決めること。
そうすると、費用も期間も自然とブレにくくなります。ここでは、名古屋の製造・内装・物流などの現場で見えてきた、費用帯と期間の目安、内訳の現実、そして失敗コストを、読み物として一気に把握できるようにまとめました。
2. まずは「相場」を“帯”でつかむ
相場は一本の数字ではなく、帯(レンジ)で考えると腹落ちします。
たとえば、単機能の置き換えや一部工程の見直しなら300〜600万円でまとまることが多く、期間は2〜4ヶ月が目安。
受発注と原価、請求までを二〜三領域つなぐなら700〜1,200万円、4〜8ヶ月がリアリティです。
全社の基幹に踏み込み、在庫や工程、WMS(ウェアハウス・マネジメント・システム)、会計連携まで視野に入れるなら1,300万円以上・最長1年弱という構図。
もちろん、名古屋の商習慣や取引先の事情、既存SaaSとの連携可否、データ移行の難度で上下します。
ただし、「今回どこまで効かせるか」を先に決めておけば、議論は驚くほどスムーズです。(全体像はピラーページ「名古屋で失敗しないスクラッチ開発ガイド」も参照)
3. 内訳のリアル:どこにお金が流れるのか

費用は、ざっくり言うと
設計(2割)
実装+テスト(約半分)
移行と教育(2割)
PM・品質(1割)
に流れます。
設計は“図面づくり”ではなく、現場の言葉をそのままシステムの設計情報に落としていく作業。ここを丁寧にやるほど、後ろの実装が迷いません。
最も工数を食うのはやはり実装とテストですが、帳票の再現やデータの移行を軽く見てしまうと、最後に足が止まります。
たとえば、Excelの列の意味が部署ごとに違う、コード体系が長年の歴史で揺れている——この“日常のゆらぎ”を前もって整理できるかで、見積は大きく変わります。
概算は「工数(人日)×日単価+予備費」というシンプルな式で出せますが、予備費は10〜15%程度を置いておくのが安全です。
予備費は“ムダ金”ではなく、リスクを早めに潰すための燃料と考えるとよいでしょう。
4. 期間の考え方:詰まりやすい所を先にほぐす
スケジュールは「要件定義 → 設計 → 実装/テスト → 移行/教育 → 運用」の順で進みます。
詰まりやすいのは三つ。
一つめは意思決定のタイミング。
経営や現場の意思決定者が週1回30〜60分で決めていく場を持てるかどうかで、1〜2ヶ月の差が出ます。
二つめは“重い機能の早期検証”。PDF出力、バーコード、外部SaaSや会計との連携は、小さくプロトタイプ(PoC)を作って
早めに「できる/できない/時間がかかる」を確認します。
三つめは移行。得意先名の揺れや品目のコード体系は、最初のスプリントからテストデータを入れて“現実の泥”と向き合うのが近道です。
期間を短くするコツは、難しいことではありません。
MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)をA/B/Cに分けてAだけに集中する、
並行運用で早めに現場の声を取り込む、
そしてUI部品や帳票、APIのルールを先に決めて使い回す。
この三点だけで、無駄な遠回りはかなり減らせます。
5.高くつく前に知っておく「失敗コスト」

プロジェクトが膨らむ瞬間は静かにやって来ます。たとえば、途中で「せっかくだからこれも…」が積み重なると、要件膨張で20%増は珍しくありません。
最初に“やる/次期/やらない”を言葉で固定しておくと、防げます。
次に多いのは移行軽視による15%増。
Excelの便利さは正義ですが、そのまま持ち込むと“便利の歴史”ごと再現する羽目になりがち。
品番や得意先、帳票の「揺れ」を最初に揃えるだけで、終盤のドタバタは見違えます。
最後は検証不足による10%増。
PDFやバーコード、会計連携を本番直前まで触らないのは危険です。小さなPoCで先回りしておけば、見積がズレにくく、日程も守れます。
6.名古屋・愛知のスナップ実例
豊田の製造A社では、受注から手配、原価、請求までの情報が分断され、現場は進んでいるのにシステム上は未着手という“ねじれ”が日常でした。
スクラッチで工程の順番を変えずに、画面の並びを現場動線へ合わせると、投入工数は3割強の削減、未請求ロスも目に見えて減りました。
名古屋市内の内装B社は、出来高・発注・実行予算の連動が弱く、請求までの迷いが課題。写真と証憑を同じ画面で完結させる設計に変えたところ、入金までのリードタイムが約3割短縮。現場の“迷い時間”を削ることが、そのままキャッシュフローの改善になりました。
刈谷の物流C社では、棚卸に人が取られ、在庫差異の調査でさらに時間が溶けていました。不足・余剰・移動中という例外を先に設計し、バーコードと在庫アラートを組み合わせると、棚卸時間は半分、誤差は4割減という結果に。
どの現場でも、効いたのは“正義の機能を増やす”ことではなく、現実の例外に寄り添うことでした。
7.よくある質問に先回りしておきます
Q「東京と比べて費用は安いの?」
——名古屋は体制や人件費の面で抑えやすい傾向はありますが、成果は要件定義と運用設計の質で決まります。単価だけの比較はお勧めしません。
Q「ノーコードからの移行は現実的?」
——十分に現実的です。データモデルや権限、帳票を最初から“移行しやすい形”で整えておくのがコツ。
Q「VPSとクラウド、どちらが良い?」
——小さく始めるならVPS、伸ばしやすさならクラウド。鍵は監視・バックアップ・セキュリティ運用を持てるかどうかです。
8.次の一歩(資料・相談)
まずは無料相談でお気軽にご相談ください
#スクラッチ開発 #オーダーメイドシステム #DX

この記事を書いた人
株式会社ウェブロッサムの
代表:水谷友彦
中小企業の業務効率化を
デジタル戦略でサポート