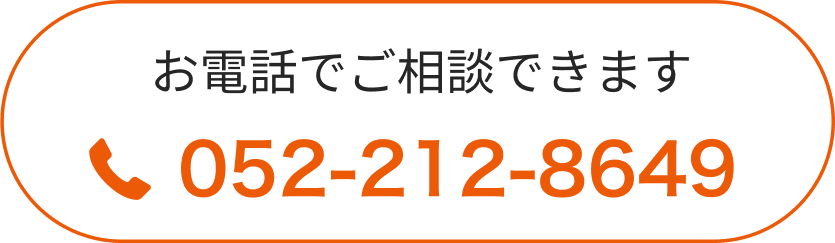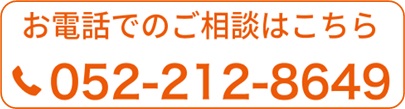ノーコードだけで大丈夫?将来を見据えてスクラッチ開発も視野に入れるべき理由
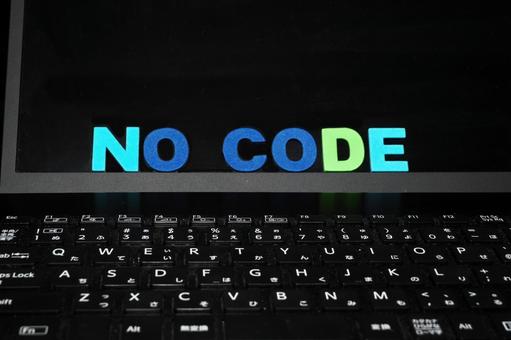
1.はじめに
近年、ノーコード・ローコードツールの登場によって、システム開発のハードルは大きく下がりました。特に中小企業やスタートアップでは、「早く・安く・簡単に」業務システムを構築できる手段として注目されています。
しかし、すべての課題がノーコードで解決できるわけではありません。
むしろ、ノーコードで始めるからこそ、将来的な「スクラッチ開発」を選択肢に入れておくことが重要です。
この記事では、その理由を解説します。

2. ノーコードは「成長初期」に最適だが「永続」ではない
ノーコードツールは以下のようなフェーズに強いです:
- 社内の課題をすぐに形にしたい
- Excel業務の代替をしたい
- 簡易な顧客管理や受発注処理を行いたい
こうした「業務改善の第一歩」には非常に効果的です。
しかし、業務が拡大し、利用ユーザーが増えたり、他システムとの高度な連携が求められるようになったりすると、ノーコード特有の“限界”にぶつかることがあります。
3. 拡張性と自由度には限界がある
ノーコードは便利である一方で、以下のような制約もあります:
- 複雑なロジック(条件分岐・例外処理)の実装が困難
- 高度な外部システム連携(API通信や独自データ構造の扱い)が制限される
- デザインやUI/UXのカスタマイズ性が低い
- 処理速度や同時アクセス数にパフォーマンスの壁がある
つまり、「業務にツールを合わせる」のではなく、
「ツールに業務を合わせる」必要が出てくるのです。
4. ツール依存リスク(ベンダーロックイン)も無視できない

ノーコードツールはほとんどがクラウド型のSaaSサービスです。つまり、
- サービス提供元が料金を値上げする
- 機能が制限されたり、終了される
- データの取り出しや移行が困難になる
といったツール依存のリスク(ベンダーロックイン)を抱えることになります。
これを防ぐには、将来的に自社の要件に合わせて作り込めるスクラッチ開発を視野に入れておくことが重要です。
5.スクラッチ開発への“引き継ぎ”を前提にした設計ができる

ノーコードでスタートしても、以下を意識しておくことで、後のスクラッチ開発へスムーズに移行できます:
- データ構造を意識して設計しておく(例:顧客、案件、売上などのテーブル)
- 各機能に対して「将来は自社開発で実装するかもしれない」と想定しておく
- 外部連携はAPI前提で設計する(後から連携しやすくなる)
こうした「ノーコード × 将来設計」の視点を持つことで、
ノーコードを「つなぎ」ではなく「踏み台」として活用できます。
6.本格的なDX推進にはスクラッチ開発が不可欠になる場合も

本格的にDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めようとすれば、
- データの一元化と活用(BI、AI、RPAなど)
- 自社特有の業務プロセスへの完全対応
- 他部署・他システムとのリアルタイム連携
- 社内外ユーザー向けの複雑なUI/UX
といった課題が立ちはだかります。
このレベルになると、ノーコードでは太刀打ちできず、専用設計されたシステム(スクラッチ開発)が求められます。
7.まとめ
ノーコードは、小規模でお試し的に業務システムを導入したい場合には非常に有効な選択肢です。スピードとコストの両面でメリットがあり、現場主導の業務改善にはぴったりです。
しかし、将来的に機能追加や業務拡大が見込まれるのであれば、後からスクラッチ開発に移行するよりも、最初からスクラッチ開発を選択肢に入れておく方が、結果的にトータルコストや移行リスクを抑えられる可能性があります。
ノーコードは万能ではありません。現在の要件だけでなく、1年後・3年後の運用イメージを持ったうえで、「最初にどう作るか」を慎重に選ぶことが、失敗しないシステム投資のカギとなります。
#スクラッチ開発 #DX #オーダーメイドシステム #ノーコード

この記事を書いた人
株式会社ウェブロッサムの
代表:水谷友彦
中小企業の業務効率化を
デジタル戦略でサポート