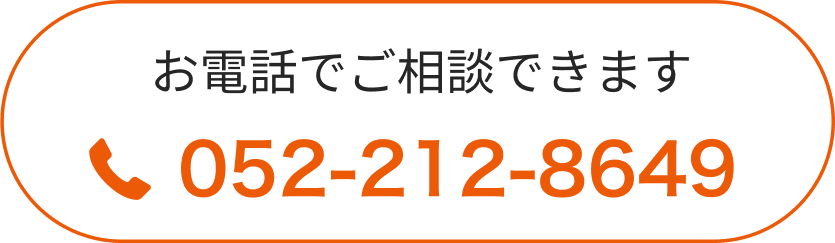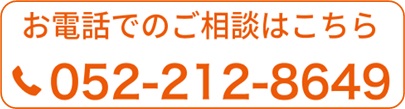DX時代に再注目される「スクラッチ開発」の価値とは

1.はじめに
2020年代に入り、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が本格的に進み始めました。「業務のデジタル化」「働き方改革」「ペーパーレス」「リモート対応」など、目的はさまざまですが、その多くが「自社の競争力を高めるための仕組みづくり」に直結しています。
こうした中で今、「スクラッチ開発(フルカスタム開発)」が再び注目される動きが強まっています。
なぜ、今「スクラッチ開発」なのか?
ここ数年、SaaS(クラウド型ソフトウェア)やパッケージソフトが隆盛を極め、多くの企業が定額課金型のシステムを導入してきました。しかし、「全社的にDXを進めたい」という段階になると、こうした既製品だけでは限界が見えてきます。

1-1. 自社の業務に合わせて“システムを変えられる”唯一の方法
多くの現場で「既存の業務にシステムを合わせたい」と思っていても、SaaSやパッケージでは機能制限や仕様上の制約が立ちはだかります。一方、スクラッチ開発では業務フロー・帳票レイアウト・ユーザーインターフェースまで、現場のリアルに即した設計が可能です。
これは、DXを“外部の仕組みに合わせる”のではなく、“自社の強みをデジタルで強化する”という、本来あるべき方向性に合致しています。
1-2. 「内製化」や「段階導入」にも強い
スクラッチ開発のメリットは、段階的なリリースや機能の追加・改修が柔軟に行える点にもあります。たとえば、まずは受発注管理だけをシステム化し、次のフェーズで在庫・売上管理といった周辺業務へ拡張していくといった進め方が可能です。
さらに、設計をしっかり行っておけば、社内SEや外部パートナーによる内製開発・保守への移行も見据えられます。これも、DX推進を持続可能にする重要な要素です。
2. 「DX = SaaS導入」では足りない理由

DXという言葉が流行語のように扱われる一方で、「とりあえずクラウドサービスを使えばDXだ」という誤解も少なくありません。
実際には、単なるITツールの導入だけでは、根本的な業務改革にはつながらないことが多いのです。
スクラッチ開発であれば、業務設計・情報整理・UI設計を通じて、“本当に必要な仕組みとは何か”を問い直すプロセスが含まれます。これは、DXの本質である「ビジネスの変革」に直結する最も重要な部分です。
3.導入事例から見る業界の動き

近年では以下のような業種で、スクラッチ開発の導入が進んでいます。
- 建設業界:独自の工程管理や現場帳票対応
- 製造業:ロット別・仕様別の複雑な生産管理
- 医療・福祉:現場ごとの記録様式や業務連携の最適化
- 不動産・リフォーム業:エリア特化型の顧客管理や進捗共有
これらの業界では、「汎用的なシステムでは対応しきれない業務の深さ」が存在し、それがスクラッチ開発の強みと一致しています。
4.今後の展望:ローコードやAI連携との相乗効果も

以前は「スクラッチ開発=高コスト・長納期」のイメージが強かったかもしれません。しかし現在は、ローコード開発環境やノーコードツールの進化により、一部機能を部品化・効率化した“ハイブリッド型スクラッチ開発”も実現可能です。
さらに、AIやIoTとの連携も前提に設計できるため、将来的な拡張性も高く、“成長し続ける業務システム”としての価値を持っています。
まとめ:自社の競争力を高める武器としての「スクラッチ開発」
スクラッチ開発は、単に「業務をそのままシステム化する」だけではなく、「業務のあるべき姿をデジタルで再構築する」ための有効な手段です。
DXを本質的に進めたいと考えている企業にとって、今こそ再び注目すべき選択肢といえるでしょう。
#スクラッチ開発 #DX #オーダーメイドシステム

この記事を書いた人
株式会社ウェブロッサムの
代表:水谷友彦
中小企業の業務効率化を
デジタル戦略でサポート