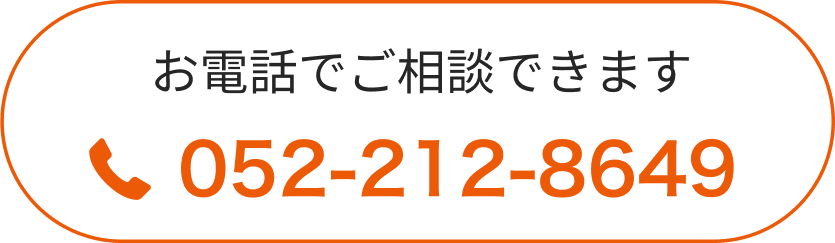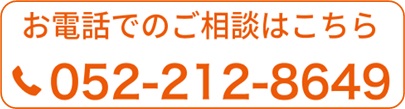SaaS全盛の時代に、なぜ今「スクラッチ開発」が再び注目を浴びているのか?

1.はじめに
SaaS(クラウドサービス)全盛と言われて久しい昨今。会計、勤怠、顧客管理、チャットなど、便利なSaaSが続々と登場し、企業のIT導入はかつてないほど手軽になりました。
しかし今、「SaaSでは解決できない課題」に直面した企業を中心に、再び「オーダーメイドのスクラッチ開発」が注目を集めています。 本記事では、その背景と理由をわかりやすくご紹介します。
2. 汎用SaaSでは業務にフィットしないという現実
SaaSは誰でもある程度使えるように設計された汎用的なツールです。だからこそ、特定の業界や現場に特有のフローには合わないことがあります。たとえば、紙とExcelで回っている受発注フローや、製造業の引当処理のような複雑な商流を、一般的なSaaSに落とし込むのは困難です。
こうした企業にとって、SaaSに業務を無理やり合わせるよりも、「業務にシステムを合わせる」というアプローチの方が、結果的に効率的で生産性も高くなります。
3.DX推進とともに高まる“自社専用システム”への期待
2018年以降、経済産業省が提唱する「DXレポート」シリーズをきっかけに、レガシーシステムからの脱却と業務のデジタル化が急速に進んでいます。中でも注目されているのが、「現場に最適化された業務システムの内製化」や「スクラッチ開発による競争力強化」です。
ノーコードやローコードといった新しい開発手法も普及していますが、それでも細かな業務要件には対応しきれないこともあります。だからこそ、自由度が高く、現場の意見をそのまま反映できるスクラッチ開発の価値が再評価されているのです。

4.SaaS疲れと「スプロール問題」への反動
複数のSaaSを導入した結果、データがバラバラになり、連携がうまく取れなくなる“スプロール問題”に悩む企業が増えています。
顧客情報はCRMに、請求情報は別の会計ツールに、
さらに業務進捗はチャットツールやスプレッドシートで管理…
というように、情報が点在する状態ではかえって管理コストが増え、生産性が下がってしまいます。
このような“SaaS疲れ”を感じた企業が、自社に必要な機能を1つに集約したスクラッチシステムの構築へと回帰しつつあります。情報の一元化と業務フローの統合という観点でも、スクラッチは有効な選択肢です。
5.スクラッチ開発が“手の届く選択肢”になった時代背景
かつては「スクラッチ開発=数千万円単位の大規模投資」といった印象がありました。
しかし今では、開発環境の進化とクラウドインフラの普及によって、比較的少額でも柔軟で実用的なシステムが構築できるようになっています。
たとえば、AWSやVPSといったクラウドサービスを活用することで、物理的なサーバーの準備が不要になり、運用コストも抑えられます。また、Ruby on RailsやLaravelといったフレームワークを使えば、開発スピードを大きく短縮できます。
さらに、IT導入補助金などを活用すれば、500〜1500万円程度の中規模スクラッチ開発も中小企業にとって現実的な選択肢となっています。
6.作って終わりではなく、育てるシステムへ

現在では、スクラッチ開発も“伴走型”の支援が主流になってきています。
つまり、最初に作って終わりではなく、業務の変化や社員の声を反映しながら、継続的に機能を改善していくスタイルです。
たとえば、新しい取引先が増えた時に必要な帳票を追加したり、業務負荷がかかっている部署だけ機能を強化したりといった柔軟な対応が可能です。
これは、あらかじめ決まった範囲しか変更できないSaaSでは実現しづらいポイントです。
7.最後に:スクラッチ開発は“コスト”ではなく“投資”である
スクラッチ開発は、初期費用が高いというイメージを持たれがちですが、長期的に見ると業務効率化や人的ミスの削減、データの一元管理など、得られるリターンは決して小さくありません。
特に「SaaSでは業務に合わない」「既存のITツールでは限界がある」と感じている方にとって、スクラッチ開発は、本質的な業務改善を実現するための“投資”と言えるでしょう。
今こそ、“本当に必要な仕組みとは何か”を再確認するタイミングです。
#スクラッチ開発 #DX #オーダーメイドシステム

この記事を書いた人
株式会社ウェブロッサムの
代表:水谷友彦
中小企業の業務効率化を
デジタル戦略でサポート