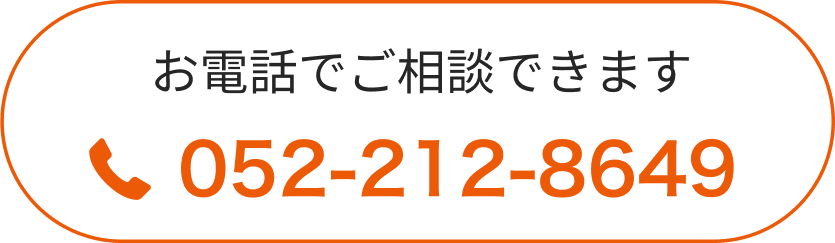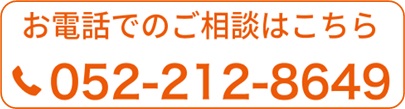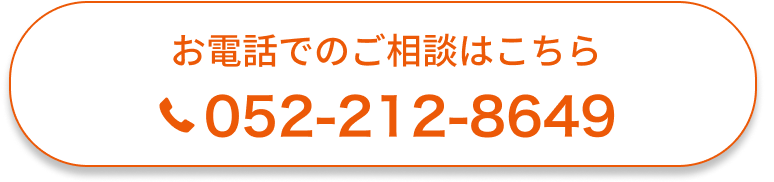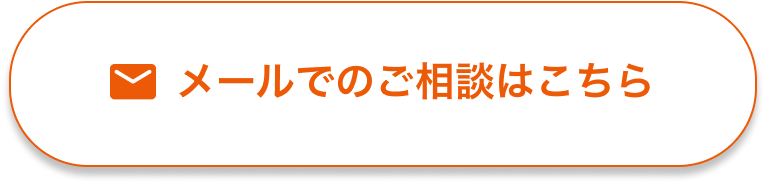補助金の“正しい入り方”:目的→KPI→要件の順で考える(名古屋版)
1.はじめに

補助金は“安く買う券”ではありません。
「何を良くするか」→「それをどう測るか」→「そのために何を作るか」の順で考え、
最後に制度に合わせて申請書を整える
——この順番が逆になると、たいてい迷子になります。
名古屋・愛知の企業でスクラッチ開発や業務システムの相談を受けるとき、
私たちが必ず最初にやるのは、制度名よりも目的と数字の確認です。
本稿は、その“正しい入り方”を読み物として一気に整理したものです。
2. まず“目的”から始める——制度名は後でいい
「IT導入補助金に通したい」「ものづくり補助金を使いたい」。動機は分かりますが、順番は逆です。
最初に言葉にすべきは、現場の詰まりや経営の課題
——何を良くしたいのか。
受発注の待ち時間か、請求までの空白か、在庫差異か。
目的が一行で言えれば、制度が多少変わっても軸はぶれません。ここで制度の要件に寄せて“やること”をいじり始めると、現場が置いてきぼりになります。
3. 次に“KPI”を決める——数字でしか話は前に進まない
目的が決まったら、数字の形に変えます。
処理時間を30%短縮、未請求をゼロ〜月1件、棚卸時間を1/2、入金リードタイムを3割短縮
——何でも構いません。
大事なのは、月次で追える指標に落とすこと。
KPIが決まると、開発の優先順位が自動で並びます。
PDFやバーコード、外部連携の順番も、KPIに効くものから実装すれば良いだけになります。
4. それから“要件”を固める——MVP(最小限のプロダクト)で十分に通用する

要件は、MVP(まず効かせる最小範囲)に絞って始めます。
受注→請求の線を先につなぐのか、出来高→請求の空白を埋めるのか、
棚卸→差異処理を軽くするのか。
A=今回/B=次期/C=やらないを先に決めると、見積もスケジュールもきれいに整います。
補助金の審査は“全部やります”より、効果が明確な最小構成のほうが説得力が出やすいのが実際です。
5. スケジュールを“制度”に合わせる——整合が命
補助金は、採択→交付決定→契約→実行→検収→実績報告という節目があります。
ここに開発の節をきれいに合わせると、資金繰りと稼働の両立がしやすくなります。
要件定義・PoC・MVPリリース・検収・報告
——各ポイントを制度の締切に重ねて計画する。
これだけで、審査側にも「計画の実現可能性」が伝わります。
6.エビデンスの作り方——“計測できる日常”を用意する
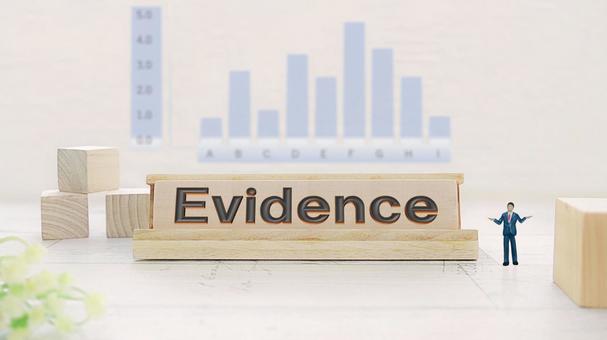
申請書で最も効くのは、美辞麗句ではなく計測の仕組みです。
作る前から、前後比較が可能な状態を準備します。
現状の処理時間、ミス件数、未請求、棚卸差異、入金リードタイム
……今の数値を一度でいいから測る。
導入後は、同じ手順で測り直す。
スクリーンショット、タイムスタンプ、ログ、写真、CSV
——“どうやって再現するか”まで書いておけば、審査も社内説得も早くなります。
7.名古屋・愛知のスナップ実例
中川区の内装B社は、
出来高→請求の空白が慢性化。「入金リードタイム3割短縮」をKPIに据え、
写真→出来高→承認の一本化をMVPに。
採択→検収→報告の節に合わせて段取りすると、初回から数字で効果を示せました。
豊田の製造A社は、
受注から原価までの分断が課題。
「投入工数3割減」をKPIに、受注→請求の背骨を先に整備。
棚卸や工程計画は次期扱いに回し、短期で成果→次期で拡張の王道で進めました。
名古屋市内の商社C社は、
在庫差異の深刻化に悩み、「棚卸時間1/2・差異4割減」をKPIに設定。
循環棚卸と差異台帳のMVPで申請し、CSV連携→API化の段階設計を示して評価を得ました。
8.よくある質問に先回りしておきます
Q. 制度選びはいつやる?
A. 目的とKPIの確定→MVP要件の素案が出た後で十分です。その方が制度の変化に強く、申請書も自然に書けます。
Q. ノーコードから始めても申請に不利?
A. 不利ではありません。“MVPで効果を見て次期で拡張”というストーリーは、
審査側にも理解されやすいです。
Q. 実績報告が大変と聞きます。
A. “前後比較が取れるログ”を最初に仕込めば、後は月次で自動集約するだけ。
スクショとCSVの取り方ルールを運用に組み込みます。
9.次の一歩
まずは無料相談でお気軽にご相談ください
#スクラッチ開発 #オーダーメイドシステム #DX

この記事を書いた人
株式会社ウェブロッサムの
代表:水谷友彦
中小企業の業務効率化を
デジタル戦略でサポート